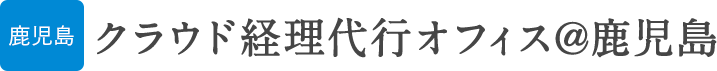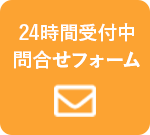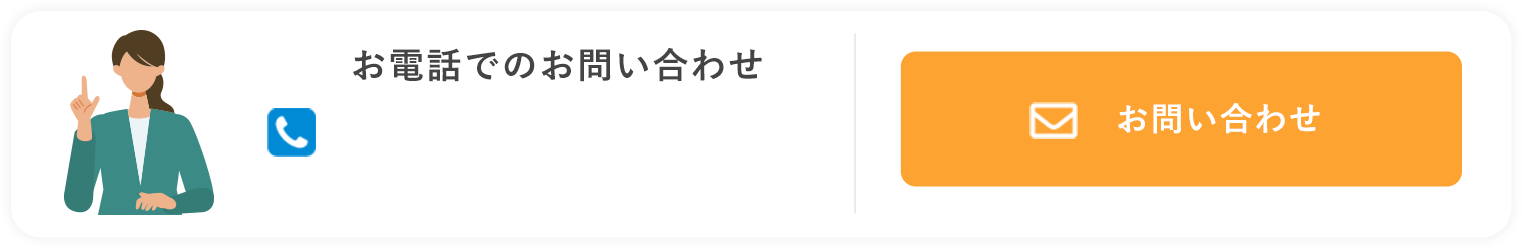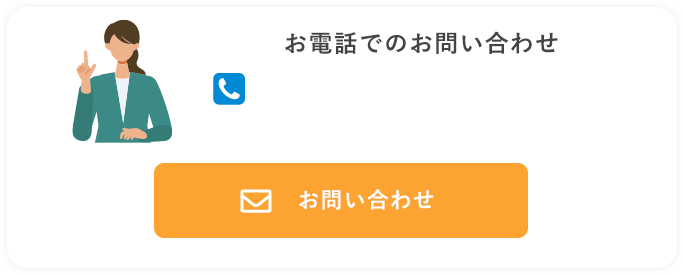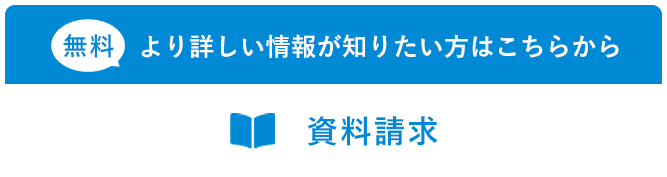【2024年1月から開始】電子帳簿保存法って結局なにをすれば良いの?
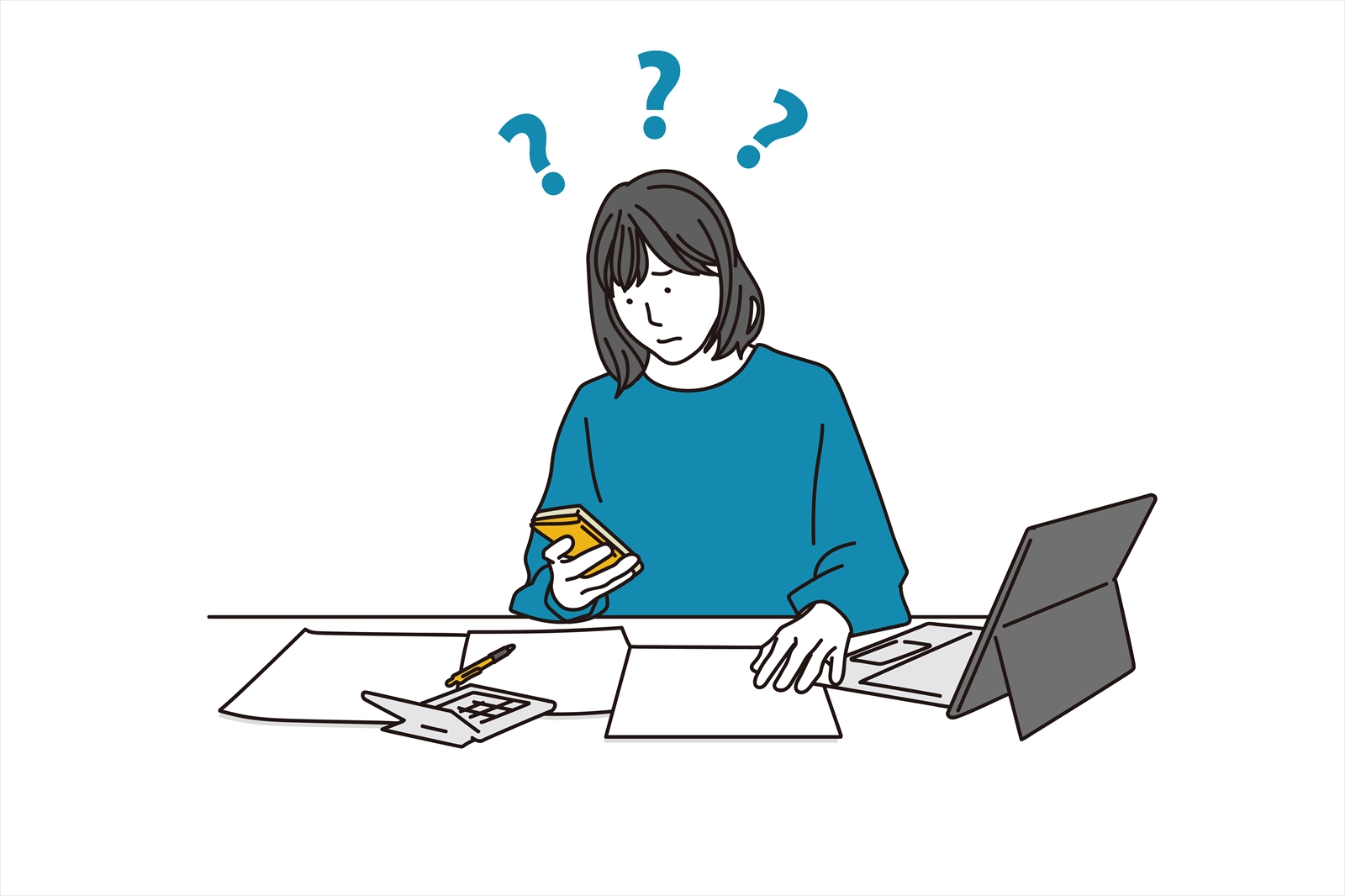 「電子帳簿保存法」という言葉を耳にしたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか?
「電子帳簿保存法」という言葉を耳にしたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか?
電子帳簿保存法は、1998年7月に施行された法律です。
その後に複数回の改正が行われ、2022年改正により電子取引における電子データ保存が義務化されました。
2023年12月31日までは猶予期間が設けられていました。
そのため、猶予期間が終わった2024年1月1日から対応しましょう!
本記事では、電子帳簿保存法に対応するための準備や影響等について紹介していきます。
電子帳簿保存法とは?改正点を解説
電子帳簿保存法とは、帳簿や決算書、請求書など帳簿・書類を、一定の条件を満たせば従来の紙媒体の保存に代わり、電子化して保存することを認める法律です。
具体的には、会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータ保存しておく方法や、 紙で受け取った 請求書をスマホで読み取って保存しておく⽅法などがあります。
また、 取引先と紙ではなくデータで請求書・領収書などをやりとりした場合の保存も対象です。
電子帳簿保存法で対象とするデータには以下の3種類があります。
①電子帳簿保存・・・仕訳帳等の取引の記録や決算書等
②スキャナ保存・・・相手から紙で受けっとた取引書類(領収書や請求書等)
③電子取引における電子データ保存・・・電子決済やメールデータ・EDI取引等
電子帳簿保存法の対応義務とは?
2024年1月からは「③電子取引における電子データ保存」の義務化がされ、罰則規定が強化されたので、企業としては順次対応していくことが必要です。
電子取引データにおいて、今までは紙で印刷したものを原本として保管できました。
しかし、2024年1月からは「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があります。
電子帳簿保存法の要件に則って保存するには、下記の【可視性の確保】と【真実性の確保】が必要です。
可視性の確保
可視性の確保のためには、下記の「モニター・操作説明書等の備付け」と「検索要件の充足」を行うことが求められます。
◆モニター・操作説明書等の備付け
具体的には、次のことができなければいけません。
①電子データの備付け・保存する場所に電子計算機、プログラム、ディスプレイ、そしてプリンタを用意するとともに、これらの操作説明書を備え付けること。
②電子データをディスプレイの画面や書面に整然とした形式、そして明瞭な状態で、速やかに出力(画面表示・プリントアウト)することができるようにしておくこと。
◆検索要件の充足
具体的には、次のことができなければいけません。
①取引年月日、取引金額、そして取引先(「記録項目」)を検索の条件として設定することができること
②日付と金額についての記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
③2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
「2課税年度前の売上高が5,000万円以下の方」または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先毎に整理している方」は、
税務調査の際などに電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば「検索要件の充足」は不要です。
真実性の確保
真実性の確保のためには、下記①~④のいずれかを行うことが求められます。
①タイムスタンプ(※注1)が付与された電子データを受け取ること
→ 取引相手によってタイムスタンプ(※注1)が付された電子データを受け取る場合
②保存するデータにタイムスタンプ(※注1)を付与すること
→ 取引情報の授受後一定期間内に自らタイムスタンプ(※注1)を付すもの
③データの授受と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで行うこと
→ 例えば、要件を満たすクラウドサービスで取引相手から取引情報を受け取って、その電子データをそのクラウドシステムに保存するもの
④不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、損守すること
→ 事務処理規程を作成して、保存された電子データの真実性を確保するもの
事務処理規程のサンプルはこちら
※注1 その刻印されている時刻以前にその文章が存在し(存在証明)、その時刻以降文書が改ざんされていないことを証明するもの(非改ざん証明)
参考資料:『中小企業のための電子取引データ・電子インボイス』執筆:松﨑啓介
参考資料:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf〔令和6年1月からの電子取引データの保存方法 国税庁〕
電子帳簿保存法に対応しないことによる影響
会社によっては、「システム整備が間に合わない」「人手不足」といった理由で準備が間に合わない場合があるかと存じます。
下記の⑴・⑵を満たす場合には、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。
⑴電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合。(事前申請等は不要です)
⑵税務調査等の際に、
・電子取引データのダウンロードの求め
・電子取引データをプリントアウトした書面の提示
・提出の求め にそれぞれ応じることができるようにしている場合
要は、電子取引データを消さずに保存しつつ、税務調査などの際に、電子取引データをプリントアウトした書面を渡せるようにするだけで問題ありません。
なお、保存する電子取引データの範囲は、これまで書面で保存しているものと変わりありません。
法的リスクや経営への影響を考えると、電子帳簿保存法に対応しない事の方がリスクが大きい可能性があります。
電子帳簿保存法への対応が自社で難しいは、上記の方法で対応できないか検討するようにしましょう。
まとめ
電子帳簿保存法の改正点や電子帳簿保存法の対応しなければいけないことについて記載しました。
時代の変化に伴い、スキャナ保存や帳票類のデータ化、電子取引に取り組む企業が増えてきました。
ですが、小規模で事業を行っていたり、経理担当者が高齢でデジタル化に消極的・対応できない場合もあるかと存じます。
企業各々で、電子帳簿保存法の対応を理解または見直し、自社でどのように対応していけばいいのかを検討していきましょう。
また、インボイス制度や電子帳簿保存法等の法改正がある度に、自社で教育・検討するのは困難な場合があるかと存じます。
その際は、ぜひ経理のアウトソーシングや経理システムの導入や見直しを検討することをお勧めします。